二戸市民文士劇は公募型でスタッフやキャスト集めます
なので毎回参加の方もいれば初参加の方もいます
特に初参加で演劇経験なしの方には、最初に覚えてもらいたい基礎用語があります
舞台の各名称を覚えないと命の危険に繋がる場合もあります
それでは主だった物をいくつか分類しながら紹介します
舞台用語1(舞台装置名)危険性極大につき重要
ここでは市民文化会館の実際の舞台で用いられる装置名や用語などを紹介します
緞帳
舞台の最も客席側にあり、舞台と客席を区切る大きな幕
この幕が開いた瞬間に、観客は演劇舞台という別空間に入り込みます
閉じるまで観客は演劇という非現実の空間に居ます
袖幕
舞台の袖に吊ってある幕。舞台の袖中(裏側)を隠す目的で用いる
中割幕
舞台の中ほどに位置する左右に開く引き割幕や上下に昇降する幕
舞台の奥行きを調整したり、舞台の前後を仕切るために用いる
暗転幕
緞帳のすぐ裏(舞台側)に吊られている、緞帳と同じような黒い幕
本番中の場面転換などに用いられる
バトン
舞台の天井にあり各種幕や照明機材、舞台で使う大きな釣り物(大道具)などをつるす為の棒
他いくつかありますが、以上の用語は舞台装置で小屋入り(本番会場入り)から使います。
すべてが重量物で天井に格納してあり、昇降させる際には必ず声掛けが必須です
「〇〇動きます、○○下がります、○○上がります」の声がかかった際は絶対に下に居ない事
判らなかったら袖(舞台左右側)に逃げてください
万が一接触等有れば大事故の元です
舞台用語2
大道具
舞台に置く風景や家、立木、岩、たんすなどの大きな家具など、人より大きい道具
場面によって人で運んで設置するものや、前述のバトンに吊るして昇降設置する物もある
小道具
置き道具と持ち道具がある
置き道具は各場面で装飾の為の比較的中小的な道具
持ち道具は役者が身に着けて使用するもので衣装や演技と密接に関わる
上手・下手(最重要)
客席から見て右側の事を上手、左側を下手と呼ぶ
ばみる(重要)
キャストの登場位置や道具の転換をスムーズに行う為の決められた位置のマーキング行為
張られたテープを「ばみり(テープ)」と呼ぶ
はける・出る
はける:舞台上から登場人物や道具類が袖に消える事
出る:舞台に登場すること
併せて「出ハケ」という
仕込み・バラシ
大道具や照明などの装置を舞台に作り上げたり設置することを「仕込み」
設置したものを原状復帰させることを「バラシ」
暗転(明転)
照明が消えて場面が転換すること「暗転」
照明がついたまま転換すること「明転」
他様々有りますが押えてもらいたいのはこんな所と思います
特に、上手下手は舞台上だけではなく練習中でも使います
覚えましょう、慣れましょう
以上舞台用語の紹介でした
では次回
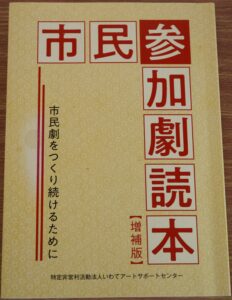
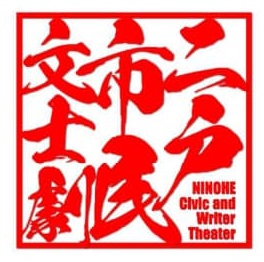

コメント